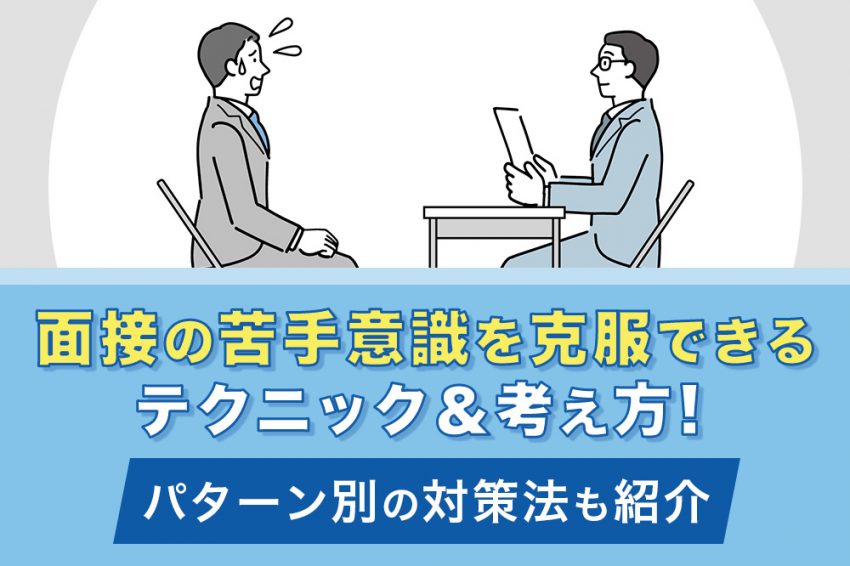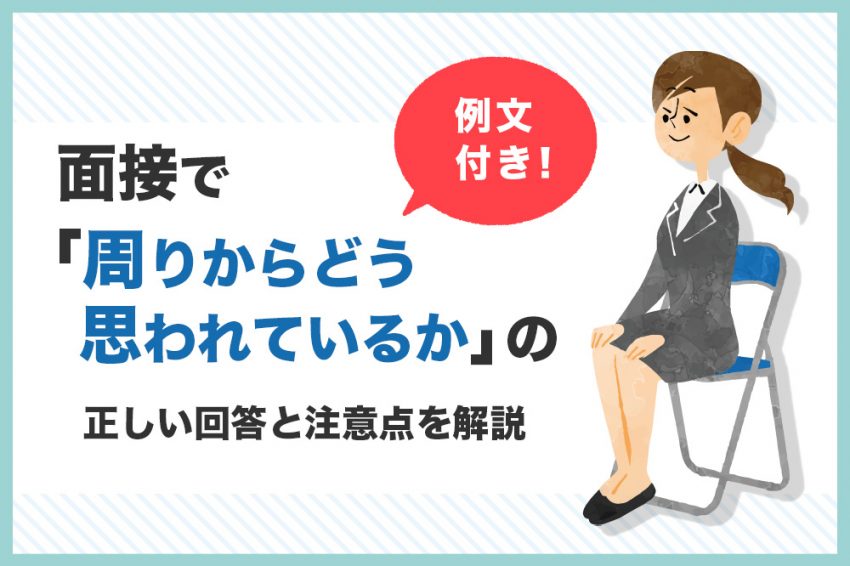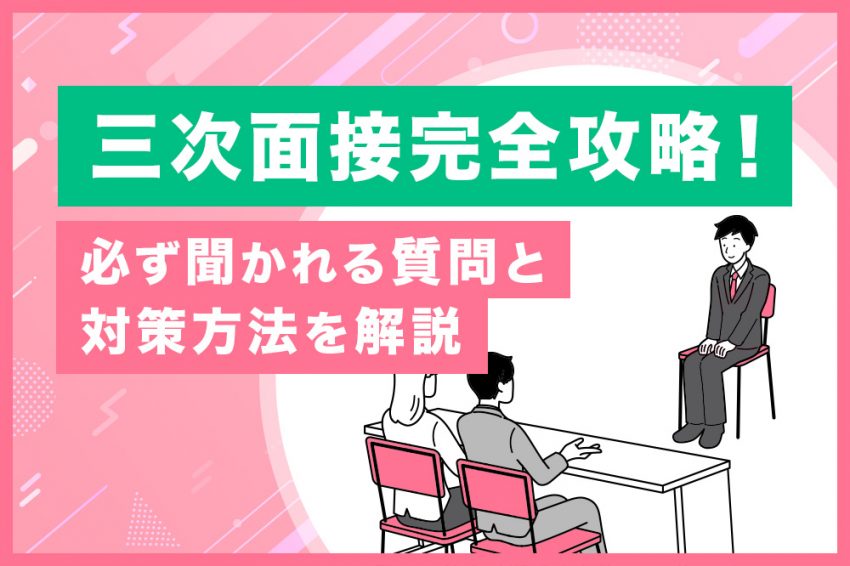楽に、ホワイト企業に入りたくありませんか?
就活キャリアでは、ナビサイトにはない、穴場ホワイト企業、隠れ優良企業の求人を
200社以上ご紹介可能。
また、自己分析の進め方や、あなたに合った企業選び、志望動機、選考対策まで
ゼロからサポートいたします。
\カンタン30秒で登録完了!/
「このコンテンツには、一部プロモーション(PR)が含まれています」
- 面接で言葉がまとまらなくて、面接が苦手に感じる……
- 面接が苦手だと、このまま就職できないかもしれない……
- 面接が苦手過ぎるから、苦手意識を克服したい!
このように、面接に苦手意識を感じてしまい、就活がうまくいかず悩んでいませんか?
面接は内定を得るうえで避けて通れないものです。その面接に苦手意識を感じているあなたは、しんどい状況でしょう。
しかし、ちょっとしたテクニックや考え方を理解して変えるだけで、苦手意識は払拭できるのです。この記事では、面接が苦手な人の特徴やそれぞれの対策方法、面接を乗り切るための考え方を紹介します。
この記事を読めば、自分がなぜ面接に苦手意識を抱いているのかを理解し、面接の苦手意識を克服できますよ。
面接で苦手意識を感じるのは自然なこと

今後の人生がかかっているような就活の面接は、自然とプレッシャーがかかり、苦手だと感じたり緊張したりするのも無理はありません。
また、大学生で面接経験を豊富に積んでいる人は多くないため、苦手だと感じるのは当然です。人は経験がない物事に対して不安や恐怖心を抱き、苦手意識を感じてしまいます。
経験のなさから「面接をやりたくない」と無意識に感じ、面接のイメージをさらに悪く持ってしまうことも。
まずは「面接は緊張するもの」「うまくできなくて当然」と前向きに考え、自分を責めないようにしましょう。反対に面接は得意だからと対策を怠り、油断をすることで、想定外の失敗を引き起こしてしまうかもしれません。
面接に苦手意識を感じてしまってもネガティブに考えないことを大前提に、自分の考え方や対処法を理解し、面接への心構えを作りましょう。
面接が苦手な人にありがちな特徴7選

まず、面接に苦手意識を感じてしまう原因について、特徴や思考の傾向を紹介します。面接が苦手な人にありがちな特徴の例は、以下の7つです。
- 緊張してうまく話せない
- 話が長すぎる・まとまらない
- 面接官に言葉が響かない、反応が薄い
- アピールすること自体に抵抗がある
- 面接に落ちることが怖い
- 自分に対して完璧を求めてしまう
- 面接に必要な準備を理解できていない
それぞれ解説するので、自分が上記のどれに当てはまるのかを考えてみましょう。
1.緊張してうまく話せない
緊張してうまく話せないパターンで、これは面接に慣れていない人によくある傾向にあります。面接に慣れていないために、緊張して自分の本心を伝えられず、面接官に響きづらくなってしまうのです。
緊張すると、リラックスして喋っている時と比べて堅い話し方になってしまうため、たとえ本当のことを話していても綺麗事や作り話のように聞こえてしまうのです。
2.話が長すぎる・まとまらない
話が長すぎる・まとまらないパターンも多く、面接に少し慣れてきて、面接の場で話すことが苦にならなくなってきた段階でありがちな失敗です。
話すことに慣れてくると、面接官に伝えたいと思っている内容が多くなり、それらの要素を詰め込んで話すため話が長くなってしまい、面接官に飽きられやすくなってしまいます。
また、要素を詰め込みすぎることでどの話を伝えたいのかが見えてこなくなり、結果として面接官の印象に残りづらくなります。
面接で自分の思いを正確に伝えるのはもちろん大切ですが、コミュニケーション能力の一環として「相手が求めている長さの回答」ができるように意識することが重要です。
3.面接官に言葉が響かない・反応が薄い
面接官に言葉が響かない・反応が薄いという人も面接が苦手な傾向にあります。
面接をしていると、自分なりに響くと思った話の内容を話しても、いまいち反応が良くないことがあります。
これは、面接官の質問の意図と自分の回答がズレていたり、その企業で求められていない答えを言ってしまっていたりする場合にあります。
前者の場合は面接官の質問の意図を汲み取れるようになることで改善できます。後者の場合は、企業の風土や事業内容について事前に細かく調べておくことで改善が期待できます。
4.アピールすること自体に抵抗がある
続いては、アピールすること自体に抵抗があるパターンです。自己主張が苦手な人や目立ちたくない人、周りに気を遣いすぎる人は、アピールすること自体に抵抗を感じやすい傾向があります。
アピールすること自体に抵抗があると、質問をされても謙遜をして自分の評価を低く伝えてしまいかねません。
また、発言に自信を持てずにネット上のありきたりな回答を重ねるなどして、説得力を失ってしまいます。
面接は自分自身をアピールする場のため、アピールすること自体に抵抗がある人にとっては、どうしても苦手意識を感じてしまう環境でしょう。
5.面接に落ちることが怖い
面接に落ちることが怖いことから、面接に苦手意識を感じるようになった人もいるでしょう。面接に落ちることによって、自分自身を否定された気持ちになってしまう人も少なくありません。
自分が傷つくのが怖いという感情から、面接に落ちるのを避けようとしている状態なのです。
自分を否定されたくない気持ちから理想の学生像を演じてしまうと、自分らしさが出せずに面接がうまくいかず、悪循環を生んでしまうでしょう。
就活が不安で怖いと感じる理由と、対処法や考え方について以下の記事で紹介しています。面接に不安を感じやすい人は、参考にして不安を克服しましょう。

6.自分に対して完璧を求めてしまう
自分に対して完璧を求めてしまい、面接が苦手になってしまったケースです。
自分に対して完璧を求めてしまう人は、少しの失敗でも怖がりネガティブになってしまうため、面接に苦手意識を感じてしまう人も多いでしょう。
面接で良い印象を与えたい気持ちは誰しもが持っていますが、必要以上に自分にプレッシャーを与えることで、緊張で頭が真っ白になってしまいます。
また、完璧を求めてしまう人は回答を一字一句丸暗記する傾向にあります。
少しでも言葉が詰まると、何を話していいのかわからなくなり、一度のミスで面接中にあきらめてしまう人もいるでしょう。
7.面接に必要な準備を理解できていない
面接に必要な準備を理解できていないことによってなかなか面接に受からず、苦手意識が芽生えてしまった人もいます。
面接に必要な準備が何かを正しく理解していないことから、自分ではやっているつもりになり、面接に通過できなくなっている状態でしょう。
特に質問に対する回答への準備不足により、その場の思いつきで回答をしてしまい、失敗する場合が多いです。
面接官は何人もの就活生を相手にしているので、答え方で準備不足だとすぐにわかってしまいます。
自分では準備をしているつもりのため、面接に落ちても何が悪かったのかのかがわからないまま苦手意識を感じてしまうケースもあるでしょう。
面接の苦手パターン別の対策法

ここでは、前述で紹介したパターンごとに対策法を解説していきます。面接の苦手パターンについて、自分が当てはまる特徴を理解したうえで対策を行いましょう。
苦手意識を克服するためには、苦手だと感じる原因に対して適切な対策法を理解し、実践することが大切です。
少し意識をすることで考え方が変わり、面接をうまく乗り切れるようになりますよ。
詳しく紹介するので、自分に合った面接の対策法を参考にして、自信を持って面接に臨みましょう。
1.緊張してうまく喋れない場合の対策法
緊張してうまく喋れないパターンの対策法は以下の3つです。
- インターン選考や本選考を通じて面接の場数を踏む
- OB・OG訪問を通じて年上との会話に慣れる
- 質問を誘導するような回答をする
順番に解説します。
#1:インターン選考や本選考を通じて面接の場数を踏む
単純に何度も面接を行えば、次第にどのように話せばいいのかがわかってきて、緊張することも少なくなります。
これを実行する場合は、本当に行きたい企業でなくても積極的に面接を受けてみるのがおすすめです。
面接に慣れたり知見を広げられたりするだけではなく、万が一内定を獲得できれば志望業界の内定が手に入らなかったときの保険にもなるからです。
ただし、面接に慣れることを優先して本当に行きたい企業の試験を疎かにしないよう注意しましょう。
面接の練習は一人でも可能です。一人での面接練習の方法を知りたい人は、こちらの記事をご覧ください。

#2:OB・OG訪問を通じて年上との会話に慣れる
面接で緊張する要因として、今までは学校で年の近い人とすごす時間が大半であり、年上の人との接し方がわからないということが挙げられます。
両親や教師も年上の人ですが、身近な存在のため練習にはなりづらいです。
そのため、企業研究も兼ねて積極的にOB・OG訪問をすることで、年上の人との会話に慣れるでしょう。この他にもアルバイトをしてみると、年上の人と接する機会も増えるのでおすすめです。
OB訪問の具体的なやり方についてはこちらの記事をご覧ください。

#3:質問を誘導するような回答をする
面接では、ある程度聞かれるであろう質問に対して回答を用意しておくという手法を取るのが効率的です。
しかし、面接で想定していない質問をされてしまうとあらかじめ用意しておいた質問の回答が使えず、緊張してうまく話せなくなってしまうケースがよくあります。
こうした状況は、質問を誘導する「フック」を用意することである程度対処できます。
フックとは、自分が用意した回答を話せるように面接官の質問を誘導するテクニックのことです。
たとえば、リーダーシップの強みをアピールしたいのならば、「私の強みはリーダーシップです。この能力は、アルバイトをしていたときに直面した問題に同僚と共に解決した際に身に着きました」と話します。
すると面接官は「どのような問題に直面したのですか?」と問いかけてくるので、あらかじめ用意した回答を話せるのです。
このように質問を誘導するフックを使いこなせれば、自分の想定内の質問で面接を進められる可能性が高くなります。他にも面接で緊張する場合の対策を詳しく知りたい人は、こちらの記事をご覧ください。
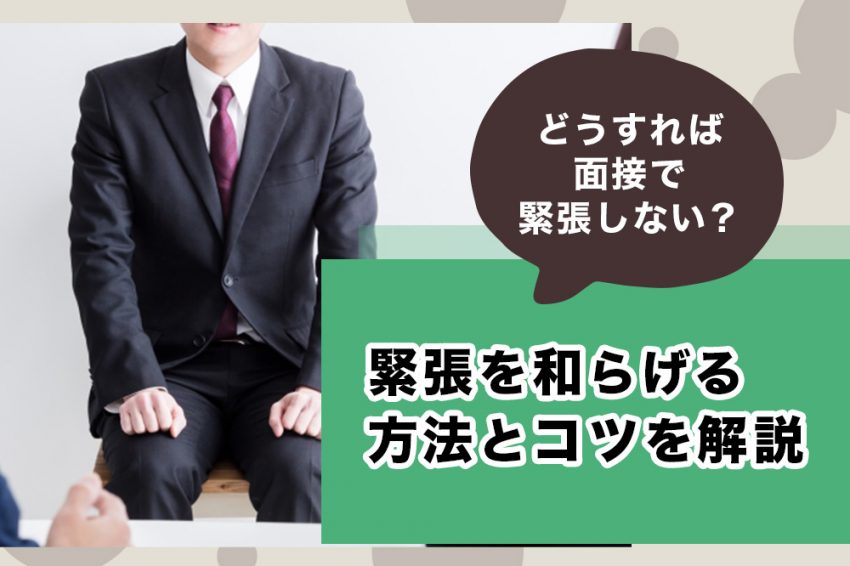
2.話が長すぎる・まとまらない場合の対策法
続いては、話が長すぎる・まとまらない場合の対策法です。
この問題を対処するにはPREP法を用いて回答するのがおすすめです。PREP法とは、結論、理由、具体例、結論をまとめて作られた文章のことです。
最初に結論を書き、次にその理由を述べた後に具体例を説明し、最後に結論でまとめます。PREP法を使うことで話が冗長になったり、伝えたいことが分散してしまうのを防げます。
面接に挑む前に、予め話す内容をPREP法に沿って書いておきましょう。
PREP法を用いた志望動機の書き方を知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
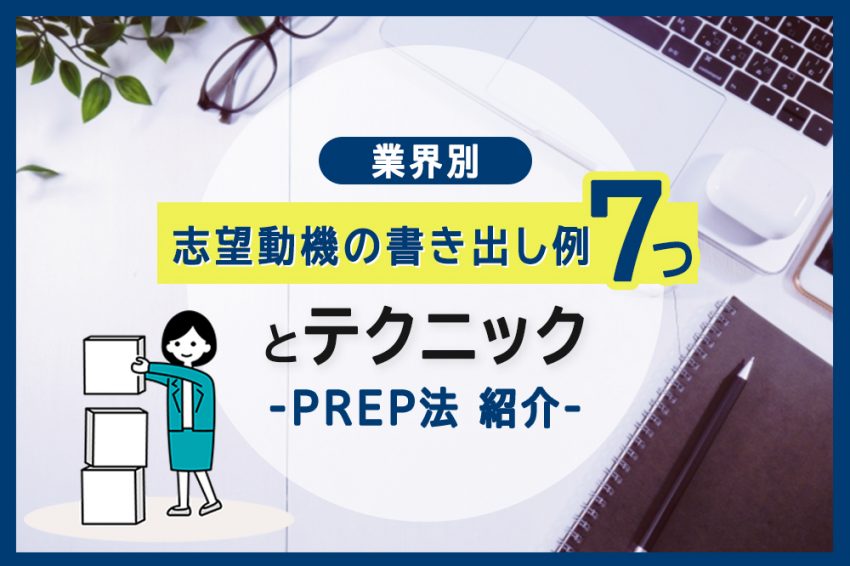
3.面接官に言葉が響かない・反応が薄い場合の対策法
続いて、面接官に言葉が響かない・反応が薄い場合の対策法です。この場合の対策法は以下の3つです。
- 面接での質問の意図を把握する
- 回答に具体例をつけ加える
- 徹底的に企業分析をする
順番に解説します。
#1:面接での質問の意図を把握する
面接はただ聞かれて事に対して答えをいうのではなく、面接官がその質問を出した意図を掴むことが大切です。
そのためには本などで面接の質問を把握し、それによって何を問われているのかを把握しておきましょう。
たとえば、「あなたの短所はなんですか」という質問の場合は、短所を知りたいという意図以外にも、以下のような意図があります。
- 面接官が思い描く短所と擦り合わせて、自分のことをよくわかっているか確認する意図
- 短所を克服する意欲があるかを確かめる意図
このように質問の意図に対して的確に答えられるように準備すると、面接官に言葉が響くようになるでしょう。企業側の質問の意図を知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
この記事ではエントリーシートでの設問の意図を解説していますが、面接の質問にも同じように活かせますよ!

#2:回答に具体例をつけ加える
回答に具体例をつけ加えることも大切です。
面接時に抽象的な考えや理想ばかり話していると、面接のために回答を準備したということが透けて見えてしまい、嘘を言っていると思われてしまうこともあります。
そのままだと説得力に欠けて面接官に響かないため、人柄や能力を証明する具体例なエピソードを加えることで、説得力やリアリティが増すようになります。
たとえば、リーダーシップのある人間であることをアピールしたい場合、「リーダーシップを取ることを常に意識してきた」という抽象的な回答ではなく以下のように回答しましょう。
- 「〇〇サークルの代表として〜をしたときやアルバイトのイベント運営など、常にチーム全体をまとめてきた」
このように、具体的なエピソードをつけましょう。
#3:徹底的に企業分析をする
面接では、学生が自社にフィットするかどうかが重視されています。
そのため、会社が求める人材にマッチしていない回答をすると、当然会社で活躍するビジョンが見えづらいため、内定を獲得しづらくなります。たとえば、以下のような場合は面接官に響きません。
- チームワークを重視する会社の面接で個人で成し遂げたことを前面に押し出してアピールする
- 一人ひとりが大きな裁量を持って仕事をするベンチャー企業の面接でコツコツと正確に仕事ができることをアピールする
あらかじめ説明会やOB・OG訪問などで求める人物像を把握し、それに沿った回答ができるように準備をしましょう。
徹底的に企業研究する方法がわからない人は、効率的な企業研究のやり方について解説しているこちらの記事をご覧ください。
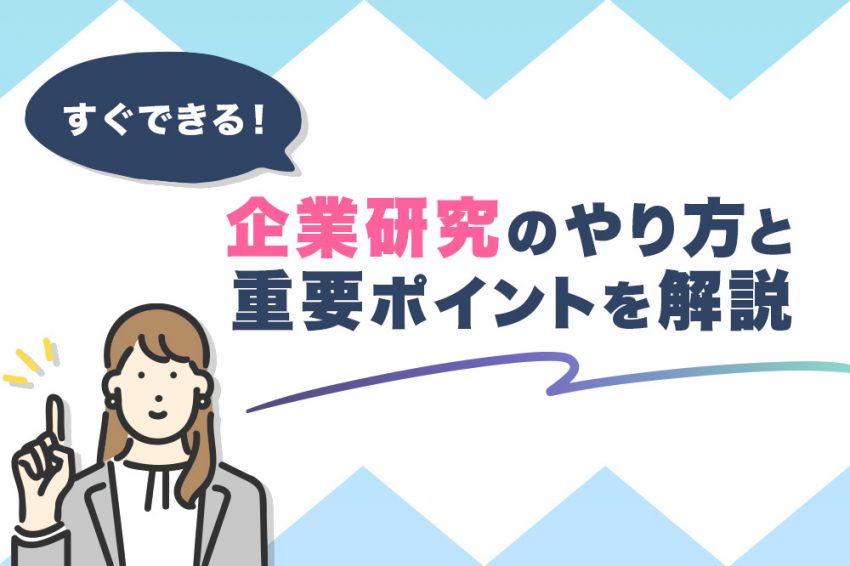
4.アピールすること自体に抵抗がある場合の対策
アピールすること自体に抵抗がある場合の対策法は、以下の2つです。
- 自分が企業に貢献できることを伝える
- 自分だけでの力ではできなかった旨を伝える
面接では就活生全員がアピールしていると理解し、差をつけられないようにしなければいけません。
謙遜をしすぎずにアピールをする伝え方を身につけましょう。順番に解説していきます。
#1:自分が企業に貢献できることを伝える
企業に貢献できることを伝えるという意識で話すと、謙虚さを保ちつつ同時にアピールもできます。
アピール自体に抵抗感がある人は、自慢しているような伝え方にしないことで苦手意識の払拭が可能です。
強みなどを聞かれたときに、ただ得意である事実を伝えるだけでなく、仕事や事業の発展にどのように活かせるのかを伝えましょう。
その際には、企業が求める人物像に当てはまっている強みや、仕事内容に共通する経験を探すのがおすすめです。
#2:自分だけの力ではできなかった旨を伝える
自分だけの力ではなく、「周囲の協力があり、周囲を巻き込んだからこそできた」と伝えることで、アピールへの抵抗感を減らせます。
学生時代に力を入れたことや自己PRなどのエピソードを話す際に、意識して取り入れてみてください。
過度な謙遜にも聞こえず、長所と同時に人間力や周囲とのコミュニケーション力もアピールできますよ。ただ、「自分の力があったからこそ達成できた」とわかるように話すことが大切です。
他力本願で成し遂げたわけではなく、あくまでも自分の意思や行動に周囲が協力してくれた結果であることを伝えましょう。
5.面接に落ちることが怖い場合の対策
面接に落ちることが怖い場合の対策法は、以下の3つです。
- 面接官と合わなかっただけと考える
- 自分自身が否定されたわけではないと考える
- どうしようもできない理由で落ちることもあると知る
面接に落ちたからといってあなた自身のことを否定しているわけではないため、傷つく必要はありません。
「面接に落ちる=傷つく」の意識をなくすことが大切です。一つずつ考え方を理解し、面接に落ちることへの不安や恐怖心を払拭させましょう。
#1:面接官と合わなかっただけと考える
面接の合否は面接官との相性で決まる場合もあるため、「今回は価値観が合わなかった」と考えることが重要です。
面接は就活生の良し悪しを判断しているのではなく、お互いが仲間として歩んでいけるかを確認する場。落ちたとしても、単にその企業や面接官と合わなかっただけと考え、割り切ることで恐怖心が和らぐでしょう。
企業の求める人物像に合わせた回答をしていても、雰囲気やコミュニケーションの取り方が組織とは合わないと判断される場合もあります。
他人同士では、感覚や意見が異なるのは当然だという意識を持つようにしてみてください。
#2:自分自身が否定されたわけではないと考える
上述の通り、面接は企業との相性で決まる部分があります。
そのため、落ちたからといって自分自身の存在や経験が否定されたわけではなく、単に合わなかっただけと考えることが大切です。
極端に落ち込んで引きずることや、傷つく必要はありません。また、一つの企業に落ちても自分の意見を取り繕わないようにしましょう。
仮に複数の企業で同じような回答をした場合、好印象に受け取る企業もあれば自社とはマッチしないと受け取る企業もあります。
企業からマッチしてないと判断されたら、自分から見ても合う企業を見つけるイメージで次に臨んでみてください。
#3:どうしようもできない理由で落ちることもあると知る
面接は、企業側の事情で落とされることもあると理解しましょう。
たとえば、採用予定の男女比による人数調整や経営状況が変化したなど、候補者へは正直に言いづらい不採用理由もあります。
自分ではどうしようもできないことなので、落とされることにショックを受けすぎないことが大切です。
落ちた理由がわからない場合は、反省をしたとしても自分を責めすぎずに受け止め、他企業の面接につなげましょう。
就活の面接で落ちる原因や評価基準、受かるためにすべき対策について知りたい人は、以下の記事を読んで、参考にしてみてください。
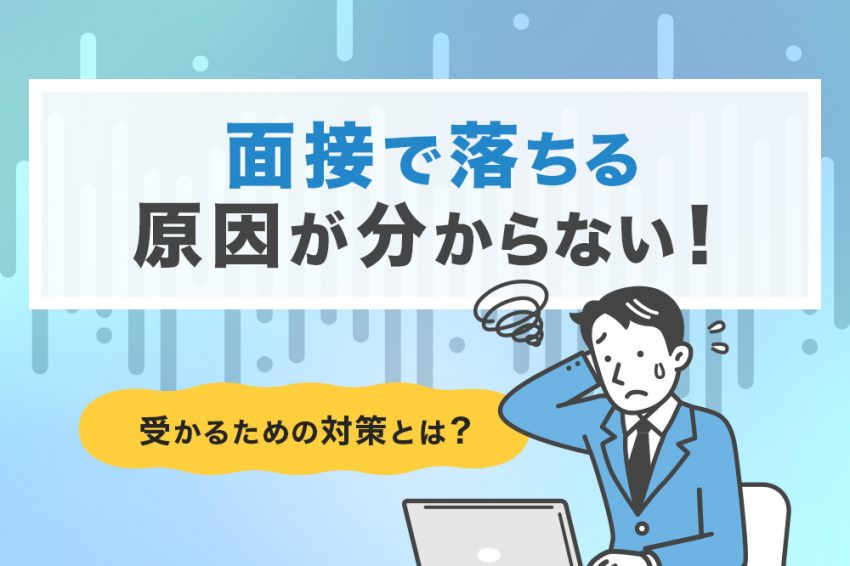
6.自分に対して完璧を求めてしまう場合の対策
自分に対して完璧を求めてしまう場合の対策法は、以下の3つです。
- 言葉に詰まること自体は問題ないことを理解する
- 聞き返すことで評価が下がるわけではないと知る
- 覚えてきたことを一字一句完璧に話そうとしない
面接でうまくいかないのは当然であり、面接官も就活生の緊張感はわかっています。自分にプレッシャーをかけず、リラックスして臨みましょう。
#1:言葉に詰まること自体は問題ないことを理解する
面接で質問に答える際には、必ずしもスラスラと話す必要はなく、言葉に詰まること自体は問題ないと理解することが大切です。
自分に完璧を求めてしまう人の中には、言葉が詰まってしまうのは悪いことだと考える人もいるでしょう。
しかし、伝えたいことをしっかりと伝え、自分の人柄が面接官に伝われば、少し言葉に詰まる程度で気にする必要はありません。また、一つの回答で全てを伝え切ろうと考えないようにしましょう。
面接官はさまざまな質問から、総合的に就活生の人柄を知ろうとします。
一度言葉に詰まっても、面接内で挽回する気持ちで最後まで乗り切りましょう。
#2:聞き返すことで評価が下がるわけではないと知る
面接で、質問の意図がわからなかったり、聞き取れなかったりした場合、「もう一度質問を伺ってもよろしいでしょうか?」と聞き返しましょう。
聞き返すのは悪いことではなく、それが原因で評価が下がるわけでもありません。うまく聞き取れなかった旨を伝えたうえで、素直に聞くことが大切です。
むしろ聞き返すことよりも、聞くことをためらって質問の意図とズレた回答をするほうが評価を下げてしまいます。
聞き返しても、「集中していない」「理解力がない」と評価されることは稀であると理解し、焦らずに冷静な対応を心掛けましょう。
#3:覚えてきたことを一字一句完璧に話そうとしない
面接対策として、質問ごとに回答を準備し、本番までに暗記していこうとする人も多いです。
しかし、覚えてきたことを完璧に話す必要はないため、一字一句間違えないように暗記するのは止めましょう。
丸暗記した回答を話すと逆に不自然になってしまい、就活生の本来の姿が見えないと面接官が感じる場合もあります。完璧すぎないほうが、人間らしさを感じられて好印象を与える可能性もあるでしょう。
そのため、伝えたいポイントをしっかりと覚えて、その場の自分の言葉で思いを伝えることが大切です。
緊張して多少文章がおかしくなってしまっても、面接官に人柄や熱意が伝われば問題ありません。
面接の準備自体は念密に行い、本番は自分らしさを大切にする気持ちを持って臨みましょう。
7.面接に必要な準備を理解できていない場合の対策
面接に必要な準備を理解できていない場合の対策法は、以下の3つです。
- まずはそれぞれの面接の特徴を理解する
- 良い第一印象を与えるためのポイントを押さえる
- 想定される質問の回答を準備する
面接に対する準備を行うことは、就活を成功させるうえで非常に重要です。苦手意識を克服するためにも、適切な準備を行い、面接の通過率を高めましょう。
この項目を参考に、自分が必要な準備を理解しているか、やったつもりになっていないかを確認してみてください。
#1:まずはそれぞれの面接の特徴を理解する
まずは、それぞれの面接のフェーズごとに求められていることを知ることが大切です。
たとえば、一次面接では身だしなみやマナーなど社会人としての基本的な要素が評価されるのが特徴で、多くの候補者から絞り込みをします。
企業ごとに合わせた対策も必要ですが、どの企業でも通用するような人間性を磨かなければいけません。ここでは、一次面接で評価されるポイントの例を紹介します。
- 最低限のマナーを理解して守れているか
- 清潔感のある身だしなみか
- 会話のキャッチボールができているか
- 明るくハキハキと受け答えができるか
上記のポイントに加えて、企業が求める人物像に合わせた自己PRを行うと高評価につながるでしょう。
それぞれの面接フェーズごとの特徴や通過率、落ちる原因について以下の記事で紹介しています。選考フェーズごとの対策を行うためにも、参考にしてみてください。
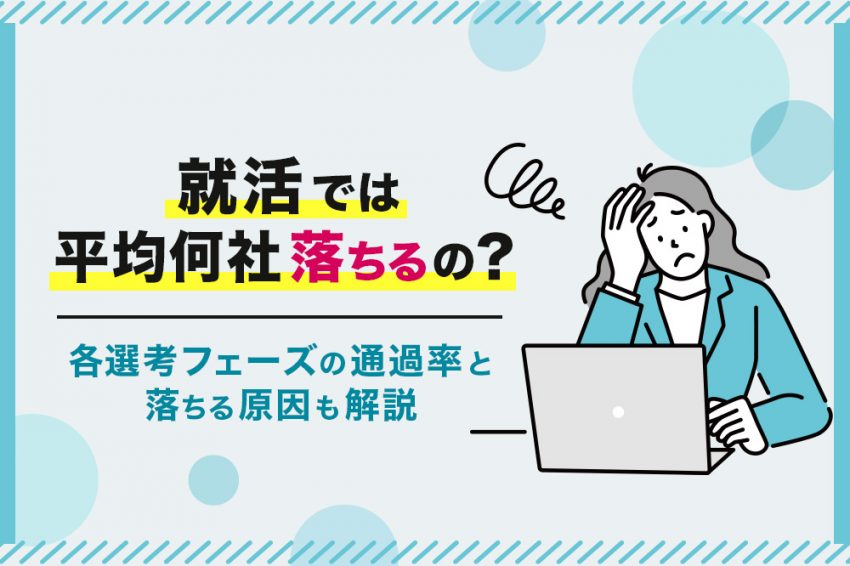
#2:良い第一印象を与えるためのポイントを押さえる
良い第一印象を与えることは、面接通過のために重要なポイントです。
第一印象で悪い印象を与えてしまうと、後から払拭するのが難しくなり、練習の成果が出にくくなるでしょう。良い第一印象を与えるためのポイントは、以下の通りです。
- 髪型やメイクは清潔感を意識する
- 表情がわかりやすい髪型にする
- 自然な笑顔で話す
- ハッキリと大きな声で話す
- マナーや礼儀を守る
自然に良い印象を与えるのは簡単ではなく、直前の練習だけでは身につきません。面接に向けて、普段から応募職種に必要なスキルの向上と一緒に練習を繰り返していきましょう。
#3:想定される質問の回答を準備する
どの企業に対しても、想定される質問の回答を準備しておくことが大切です。その場で思いつきの回答をしていては、質問の意図に沿った回答をするのが難しくなります。
面接官にもバレてしまい、「やる気がないのかな」とネガティブな印象を与えかねません。ここでは、就活の面接で想定される質問の例を紹介します。
- 自己紹介をしてください
- 志望動機を教えてください
- 強みと弱みは何ですか?
- 学生時代に力を入れていたことはありますか?
- 何か質問はありますか?
結論ファーストを意識し、それぞれの回答に一貫性を持たせることを意識しましょう。面接で頻出する質問の類型、それぞれの質問と回答の例文について、以下の記事で紹介しています。
質問の意図を理解して、回答を準備しましょう。

面接が苦手なら就活キャリアを利用してみよう
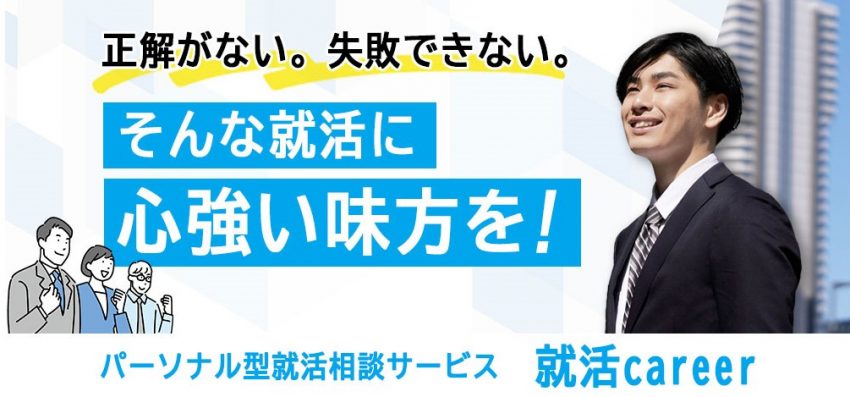
- 面接の苦手意識がなくなるようサポートしてもらいたい
- 苦手な面接を克服する方法が知りたい
自分一人で就活を行うのではなく、就活エージェントのサポートを受けながら行うことで、早く内定獲得を目指せます。
就活エージェントは、プロの就活アドバイザーがマンツーマンであなたを内定までサポートしてくれるサービスです。
就活に関する相談やESの添削、面接対策や練習も無料で行ってくれますよ。しかし、「就活エージェントといっても多くてどれを選べばいいかわからない」という人もいると思います。
選び方に悩んでいるなら、「就活キャリア」を利用してみませんか?
就活キャリアには、国家資格保有者や元人事担当者のアドバイザーがいて、あなたの内定獲得を徹底サポートします。
豊富な内定支援実績からあなたの希望や適性、能力に合った企業を紹介できますよ!就活相談はオンラインで行っているため、全国どこからでも受けつけています。
無料で利用可能なので、まずは気軽に相談してみてください。
\カンタン30秒で登録できる!/
面接前に意識すべき!面接を乗り切るための考え方4つ

面接に対する苦手意識を払拭するためには、克服するための考え方を理解し、受け入れることが必要です。面接を乗り切るための考え方として、以下の4つを紹介します。
- 失敗しても挽回は可能
- うまく話そうと考えすぎない
- 多少の緊張はあるほうが良い
- 面接官も普通の人であることを理解する
選考の中でも面接を特別視せず、意識しすぎないようにしましょう。捉え方や意識が変われば、苦手意識がなくなり、自信を持って面接に臨めるようになりますよ。
それぞれ解説していきます。
1.失敗しても挽回は可能
面接で緊張してしまい、失敗をしても挽回は可能であると理解しましょう。一度失敗したら終わりだと思い、あきらめてしまう人もいますが、全くそんなことはありません。
失敗を恐れるのではなく、素早く切り替えて面接内でどうリカバリーするかを考えることが大切です。
多少失敗しても、素直に間違ってしまったことを伝えて言い直したり、熱意を込めて話したりすると、最終的にプラス評価で終わる場合もあります。
ちょっとしたミスからあきらめモードになり、不合格になったら苦手意識を持ってしまうなど、悪循環にならないように気をつけましょう。
2.うまく話そうと考えすぎない
良い印象を与えたいからといって、うまく話そうと考えすぎる必要はありません。「うまく話せた=面接に受かる」わけではなく、自分らしさや思いを伝えることが内定につながります。
面接官からすると、就活生の人柄や考え方が自社にマッチしているかが重要なポイントです。多少文章や敬語がおかしくなってしまっても、緊張していることを素直に伝えれば評価が下がることはありません。
面接官も就活生の緊張は理解しているため、正直に伝えていくことで人間らしさが評価されることもあるでしょう。
マナーや礼儀は意識しつつ、質問の回答は相手に伝えることを意識して臨むことが大切です。
3.多少の緊張はあるほうが良い
多少の緊張は、気持ちを引き締めて良いパフォーマンスを出すのに必要な要素です。緊張するからと面接に苦手意識を感じる人もいますが、緊張すること自体を恐れる必要はありません。
緊張感のない状態で面接をすることで、逆に悪い印象を与えてしまう可能性もあります。多少の緊張は持っていて良いと理解しながら、面接に臨みましょう。
ただ、緊張しすぎると、自分をうまく出せなくなりマイナスに働いてしまうため、対策を考える必要があります。
この記事でも紹介しているように、場数を増やしたり年上の人との会話に慣れるようにしたりと、面接対策を行ってみてください。
4.面接官も普通の人であることを理解する
面接官だからといって特別な人間なわけでなく、ごく普通の社会人です。身の周りにいる大人たちと同じなので、すごく目上の存在だと必要以上に意識する必要はありません。
面接官を特別視しないことで緊張も減り、苦手意識を払拭できるでしょう。また、面接官は人事が担当することも多いですが、現場の人が担当する場合もよくあります。
相手が必ずしも面接に慣れている人間ではなく、お互い緊張している可能性があるかもしれません。
「たまたま今回はこの人が面接官として座っている」と、1人の人間と話すイメージで臨むといいでしょう。
面接が苦手な人が注意すべきポイント2つ

ここからは、面接が苦手な人が共通して注意すべきポイントを紹介します。今回紹介するのは、以下の2つです。
- 面接官の様子をしっかりと見ること
- 話す内容だけではなく話し方にも注意する
順に説明します。
1.面接官の様子をしっかりと見ること
面接の際は、ただ漠然と面接をするのではなく、面接官が自分の回答や態度に対してどのような反応を示しているのか、その様子をしっかりと見ることが大切です。
面接官が飽きていたり、関心を持っていない様子だったりしたら今話している内容はすぐに切り上げたり、聞こえづらそうにしていたら声のトーンを上げるなどしましょう。
面接官の様子を常に見て、求められていることが自然に実行できるようにしましょう。そのためには、面接の場数を踏むことが一番の近道です。
何度も面接をする中で観察力を身に着けてから本番の志望企業での面接に挑みましょう。
2.話す内容だけではなく話し方にも注意する
面接でありがちなのが、話す内容を論理的に・わかりやすく伝えようとすることにばかり意識が行ってしまい、話し方に意識が回らなくなってしまうことです。
内容に意識を集中すると、早口になったり、敬語がうまく使えていなかったり、どもってしまってうまく話せなくなったりしがちです。
話の内容がどれだけ良くても、話し方が悪いと面接官の印象も悪くなってしまいます。
姿勢を正す・笑顔で話す・はきはきと話すことは話す内容と同様、非常に重要な要素であるため、無意識に実践できるように練習しましょう。
練習として就活をしている友人や就活を終えた先輩などに面接の様子を見てもらうと、自分のどこが悪いのかがわかるのでおすすめです。
面接力診断で、苦手分野を対策しよう
今年の就活は、Web面接を行う企業も増え、戸惑っている人も多いはず。
そこで活用したいのが「面接力診断」です。24の質問に答えるだけで、自分の面接力をグラフで見える化し、集中的に対策できます。
Web面接も、通常の面接と押さえるべきポイントは同じです。ぜひ活用して選考を突破しましょう。
内定につながる自己分析ならAnalyze U+

自己分析に時間をかけすぎていませんか?自己分析で大事なのは、”企業が求める能力と自分の能力が合っているかどうか”を判断することです。
自分にどんな強み・能力があるかを素早く正確に把握できるのが、スカウト型就活サービスを提供しているOfferBoxのAnalyze U+という機能です。
Analyze U+は、自己分析の精度が高いのはもちろん、その結果に興味をもった企業からスカウトが届きます。
実際にプロフィールを80%以上入力した学生のオファー受信率は93.6%!5分で登録できるので、今すぐ登録して自分の強みを把握するようにしましょう!
\無料で自己分析/
面接の苦手意識を克服して面接を得意にしよう
この記事では、面接が苦手な人のパターン3つとパターン別の対策法などを紹介しました。
面接が苦手意識である理由は緊張しすぎることや話しすぎることなどがあり、それぞれに対策方法があるとわかっていただけたかと思います。
また、話す内容だけではなく、どのように話すかも内容と同じくらい大切だと理解できたのではないでしょうか。
この記事で学んだことを活かして自分の苦手なポイントを把握し、面接で適切なコミュニケーションができるように練習していきましょう!
就活キャリアでは、面接の練習ができたり、自分に合う企業を紹介してもらえたりなど、さまざまなサービスが無料で受けれるので、ぜひ活用してみてください。
楽に、ホワイト企業に入りたくありませんか?
就活キャリアでは、ナビサイトにはない、穴場ホワイト企業、隠れ優良企業の求人を
200社以上ご紹介可能。
また、自己分析の進め方や、あなたに合った企業選び、志望動機、選考対策まで
ゼロからサポートいたします。
\カンタン30秒で登録完了!/